
| ||
|
何か信じられるものがあることっていいことみたいに言われるけど、何かを絶対的に信じちゃったりするって危ないような気がするなあ。だってさあ、国家だとか神様とか天皇陛下だとかそういったものを絶対に信じちゃったりした結果戦争とかが起きちゃう訳だからね。だから、そういうのは程々にしておいた方がいいと思うよ。それから日本人のアイデンティティーとかそういうのも余り気にしない方がいいような気がする。何人だっていいじゃない、男だろうが女だらろうがいいじゃない。人種だとか国籍とか性別とか世間で言われている程大したもんじゃないよ。それより人間としての共通性の方が重要だと思うんだ。僕にも色々な友達がいるけど、アイルランドの友達もポーランドの友達も話をしたり付き合ったりしても全然違和感ないもの。まあ精々お互い理解できるように互いの文化とか考え方を学ぶことが大切なんじゃないかなあ。だから僕は自分の国籍だとか性別なんか全然何とも思っていない。ただの人間で充分だよ。だからオレ「根無し草」で結構。むしろそれを誇りに思っているの。 (2 April, 1999) 新入生の皆さん、入学おめでとう。えーと、こんなこと言うと頭の固い「おじん」と思われそうだけど言わせてもらいますよ。あのねえ大学に入ったからにはしっかり勉強してね。だってカッコ悪いよ、勉強しないあほ学生なんて。人生、カッコが大切なの。オレ、何時もカッコよくありたいと思っている。姿形は如何ともし難いけど、生き方とか何とかはどうにかなりそうだからね。それで本をゲが出るほど読んでね。世界のことをまっとうに知ろうと思ったら、なんやかや言っても今のところ結局活字が一番頼りになるんだからね。そうやろー、歴史でも文化でも私たちの知識の大部分は活字から得ているんだから。だからしっかり本を読んでカッコいい大学生になろうね。もちろん、遊びも大切だと思うけど、よく遊んでよく学んで下さい。色んなことに興味を持ってね。その中で自分が特に知りたいと思ったことを徹底的に学んで下さい。 (2 April, 1999) 大学って何するところなんだろう?考えたことある?最近は就職状況が悪いこともあって、大学も学生も就職のことでは躍起になっているみたい。もちろん、就職のことは大切。僕も学生には一生自立できる職業を持つべきだっていっているし、本当にそれは大切なことだと思う。それでもなお、大学って職業に就くためのワンステップに過ぎないとは思わない。Liberal Arts っていう言葉知ってる?大学の教養科目を英語でこう言うの。元々の意味はギリシャ語起源で、自由市民の教養って言う意味なんだ。奴隷は自分の仕事をするだけの知識・技能があれば事足りるけど自由市民はそれだけでは駄目で、色々なことを的確に判断したり、世界の成り立ちを知る教養が必要だと言うわけ。僕は大学と言うところは単なる職業訓練校であって欲しくないと思っている。どんな職業に就いても、人間として必要な、世界を広い視野から見据え、判断し、どうしたら世界をよくできるだとか考えたり、好奇心をもって色んなことを理解する力を身につける場だと思っているんだ。だから大学では色んなことを学んで物事を様々な角度から見る力を身につけてもらいたいと思うんだ。 (3 April, 1999) あら、タイトルがちょっと過激だったかしらん。僕たちは自分で考えていると思っていても、結構、常識とか習慣によって考えさせられていると思うんだ。一度どこかでそういう常識とか何とかを全部破壊して、その混沌の中からもう一度世界を自分の中で再構築してもらいたいと思う。破壊せよ、そうして混沌の中からもう一度立ち上がれ。 卒業生の皆さん、卒業おめでとう。これから色々なことがあると思うけど、一つだけ忘れないで欲しいことを書いておきます。ちょっと分別くさいおじさんのお話みたいで嫌なんだけど・・・。どんな状況になっても他人の心の痛みを想像できる人間であって欲しいと思うの。自分の言葉や行為が他人に与えるかも知れない痛みを何時も考えてください。場合によっては、自分の主義とか信条から他人の心に痛みを与えなくてはならないこともあるかも知れないけど、そんな時でも、その人の心の痛みを想像できる人間であって欲しいと思うわけ。それだけちょっと言っておきます。それからこれは何時も言っていることなんだけど、強く、元気に、逞しく生きていってください。 (23 March 2000) かつて(もう一世紀以上も昔の話だ)、世界に植民地を拡大しつつあった西洋帝国主義の言説は、西洋と非西洋とを、理性的/非理性的、文明/野蛮、科学的/感覚的と言った二項対立によって認識し、未開にして野蛮なる非西洋を統治してやるという自己中心的な名目のもとに植民地支配を正当化しようとしました。このような痛ましいまでに傲慢にして貧困な論理・言葉によって、今また戦争が引き起こされました。私たちは、少なくとも、そのような貧困な言葉に対抗する言葉を鍛え上げてゆかなければならないのだと思います。実はそのような言葉を鍛えることが、学問をすることの一つの意味なのかもしれないと思うのです。 (27 March 2003) |
||
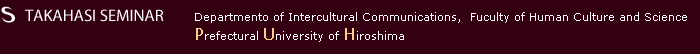
| ||
