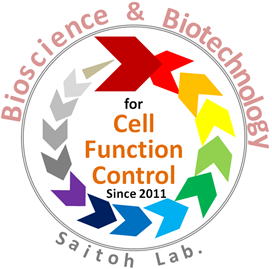県立広島大学 生物資源科学部 (庄原キャンパス)
Laboratory of Bioscience & Biotechnology for cell Function Control
はじめに(ご挨拶)Profile
担当教員紹介
生物資源科学部 生命環境学科(生命科学コース)教授
大学院 総合学術研究科 生命システム科学専攻(兼任)
生命科学科長(2019年4月~2021年3月)
生命科学コース長(2020年4月~2021年3月)
大学院 生命システム科学専攻長(2021年4月~2023年3月)
大学院 総合学術研究科長(2023年4月~)
齋藤 靖和 (さいとう やすかず) 博士(生物生産学)
Yasukazu Saitoh, Ph. D.

本学の前身である広島県立大学を卒業・修了し、企業研究所に勤務の後、県立広島大学 生命環境学部 生命科学科 助手として着任しました。その後、2011年4月より細胞機能制御学研究室を主宰しています。
これまで酸化ストレスによる細胞傷害/細胞死、がん、老化や生活習慣病とその制御を中心に研究を行ってきた経験を活かして、様々な疾患や病態を予防・改善し、人々の健康・長寿へと貢献できる新規バイオ素材の開発を目指していきたいと考えています。これまでに多くの企業との共同研究も行っており、基礎的な研究だけでなく、研究成果の社会への還元および貢献を念頭においた研究も行っています。
出身:岡山県
出身高校:岡山県立笠岡高等学校
趣味:ぶらぶらとスーパー、ホームセンター、雑貨屋、書店などを巡って新しいものや面白いものを探すこと。ドライブがてら新しいスポットやお店を探すこと。パン屋めぐり、道の駅めぐり。安くて美味しいものを発見すること。スポーツ観戦(地元チームである広島東洋カープとサンフレッチェを応援しています)。漫画、アニメ、ゲームも少々。
担当授業科目:
【学部】生物学Ⅱ、栄養化学、生体機能学(旧細胞生化学)、科学英語(専門英語セミナー)、基礎生命科学セミナー、生命科学セミナー、大学基礎セミナーⅠ、クリティカル・シンキング、生命環境科学基礎セミナー、基礎生命科学実験、応用生命科学実験、卒業論文Ⅰ・Ⅱ
【大学院】細胞機能制御学、細胞機能制御学(特論)、研究プレゼンテーション演習Ⅰ、Ⅱ、生命機能制御学実験
所属学会:
日本香粧品学会
日本薬学会
日本癌学会
日本ビタミン学会
日本酸化ストレス学会
日本抗加齢医学会
日本農芸化学会
○齋藤のこれまでの経歴について分かりやすく書いたもの
教員ロングインタビュー(齋藤教授)
教育指導方針
答えの分からない、誰も知らない未知の問に対する答えを自らの手で探し出すというのが研究の醍醐味の一つです。様々な可能性を考えて試行錯誤を重ね、粘り強くデータを蓄積するといった地道な積み重ねがもちろん必要不可欠ですが、それが実り、新しいことが分かったときの達成感や充実感を1つでも多く経験することで、研究の面白さ、楽しさを存分に味わって欲しいと思います。
そのためにも、日々の研究活動を通じて、サイエンスに対する興味を深め、学生自身が研究の面白さに気付き、率先して自ら考え、自ら行動できることができる姿勢を身につけることができるように指導していきたいと思っています。最終的には、研究活動を通じて、それぞれのいろんな才能を開花させ、社会で活躍できる人材を育成していきたいと考えています。
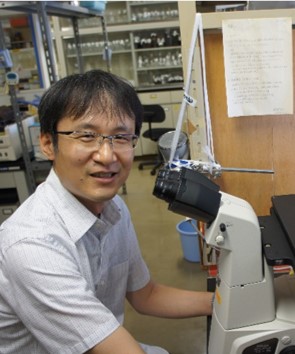
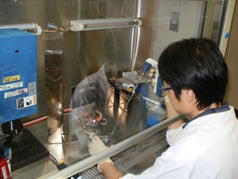
研究室活動内容
積極的に学会発表や学術誌への論文発表などにより国内外へ向けた情報発信を目指しています。
主な年間行事(予定)
4月:新加入メンバー歓迎会(BBQや花見)
6月:日本香粧品学会、酸化ストレス学会、抗加齢医学会
学内バレーボール大会
10月:学内ソフトボール大会
2月:卒論、修論発表会
3月:卒業式、日本薬学会
その他:お誕生日会、ラボ旅行、齋藤研スポーツ大会、クリスマス会、各種飲み会など
研究室内報告会、セミナー(プレゼンテーション、文献輪読)
定期的に各自の実験進捗状況を報告する研究室内報告会、自身のテーマに関する関連文献などを紹介するセミナーを行っています。
学生へのメッセージ

大学では、それまでの与えられて学ぶという受け身の学習から、自らが学びたいことを選択して学ぶという能動的な勉強へと移行していきます。ぜひ大学1,2年次の間にいろいろな学問領域にふれ、「自分はどんなことに興味があるのか」、「どんな学問分野、領域を楽しく感じるのか」、転じて「将来どういった分野の仕事/職種に就きたいのか」、漠然とでも構いませんので、日々の大学生活の中で意識しておいてほしいと思います。きっと自分の将来の方向性を決定するときに役に立つと思います。日頃からそういうアンテナを張っておくと、必ず自分の将来の方向性を決定するのに役立つと思います。
「好きこそものの上手なれ」は至言であり、自分がいいな!、楽しそうだな!と思える分野に向かってとことん打ち込んで欲しいと思います。研究は、答えの分からない、誰も知らない問に対する答えを自らの手で探すというのも醍醐味ですが、思い通りにいかないことや失敗もたくさんあります。しかしながら、失敗からも学ぶべきことはたくさんあり、試行錯誤や創意工夫によって失敗を克服するといった経験を積み重ねることは、その後の自身の生き方や過ごし方にとって大きな糧になると思います。
研究室所属の2年間で様々な経験を積み重ね、見違えるように成長していく学生はたくさんいます。是非、みなさんもその一人となって社会へと羽ばたいていって欲しいと願っています。
さぁ、我々と一緒に研究にのめりこみしましょう、新しい発見を目指しましょう、失敗や成功を繰り返して共に成長していきましょう!
齋藤研究室では、研究内容に興味があり、研究への熱意を持続できる学生の加入を歓迎しています。研究内容について詳しく知りたい、指導方針や研究室のルール等についてもっと知りたいという学生は、是非、研究室のドアを叩いてみて下さい。お互いに話をすることで、みなさんの気づきや成長の一助になればと思います。
◎当研究室に求める学生像
1)本研究室の研究テーマに興味があり、研究活動を通して自分を高めていきたいというやる気・野心のある人(研究に 意欲と情熱を持続できる人)
3)研究は楽しいばかりでなく、上手くいかず、落ち込むこと、悩むこともたくさんあります(そんなことの方が多いで す)。そういった状況におかれても活路を見出そうとするタフな精神力の人。
4)イベント好きの人(企画、参加どちらも歓迎)。
医薬品、化粧品、食品企業、美容業界、公務員、教職員などを中心に幅広い分野で活躍しています。
卒業生の一部は研究・開発分野でも活躍しています。
○齋藤研究室の研究心得(研究室メンバー、配属希望者は読んで下さい)
これから多くの時間を過ごす研究室が楽しく、気持ちよく過ごせる場所であるために・・・。
研究室での生活が社会に出るまで、出てからの自己成長ための良いステップとなるために・・・。
①共同体(仲間)としての意識
・誰かがやるではなく自らが率先して行う気持ちが大切。
・やり方を知らないというのは言い訳にはならない。知ろうとする気持ちと行動が大事。
・研究室の外に対してはひとりひとりが「研究室の顔」になります。特に共通機器や共通実験スペースの使用に関して は細心の注意をはらって下さい。ひとりの勝手な行動が多くの人の迷惑になりかねません。
1) 時間厳守
決められた時間には研究室に居ること。無断欠席をしない(メールか電話で事前に連絡)。
2) 事前相談
一連の実験を開始する前に、必ず「プロトコール」を作成して指導教員に提出し、事前に打ち合わせる。
3)都度報告
実験失敗の場合ほど打合せ必要度が大きい。
結果が出なくても、1週間に1回は必ず何か報告すること。
実験の途中でのトラブルは、その時に直ちに連絡する。
1)事前に指導教官と十分に打ち合わせを行うこと。
2)まずは、自分で調べる習慣をつける(自分のテーマに関すること、自分の行う実験方法など)。
3)分からない事はまず先輩や指導教官に聞く(聞くときはメモをとる)。ただし、自分で調べることのできる最低限の 事は調べておくのがマナー。
4)使用する試薬・機器についてはきちんと調べてから使うこと(使用目的、危険性、廃棄方法など)
5)実験のコストも意識すること(必要以上な量の試薬を作製するのはコストにも環境にも負荷をかけます)。事前に十 分に計画を練ってから使用するように心がけること。
6)得られた実験結果について、自分なりの考え、解釈を持ったうえで指導教官へと報告すること。失敗データも必ず報 告すること 。失敗と思っていたことがミスではなく、新しい発見につながることもあります。
7)実験の記録は必ず記録すること。第三者がみて再現できるレベルを目標に実験記録をとること。
1)みんなが協力して行う作業
掃除・ゴミ捨て
細胞廃液の処理
保存細胞株の整理・維持・管理、試薬の整理
2)当番を決めて順番に担当するもの
洗浄・滅菌
液体窒素の補充
消毒用エタノール
レクリエーション
セミナー
3)器具・試薬の在庫管理について
器具・試薬を新たに開封した人は、まずはまだ在庫があるかどうかきちんと確認する。
*在庫管理を甘く考えないで下さい。一人のいい加減な気持ちがみんなの実験に影響を与えることがあります。
4)安全管理
・研究室は危険な場所であることを意識して下さい:機器の誤った使い方、液体窒素の取り扱い、高圧ガスの取り扱い、毒劇物の使用管理、危険なゴミの存在など。
・電気・ガスのつけっ放し、水道の出っ放し厳禁! 火事や漏水の原因になります!
・無菌的操作、実験操作にふさわしい身なりを心がけて下さい。おしゃれは自由ですが、身なりは清潔に、そして状況 に応じた服装をして下さい。
・一人で夜遅くまで実験することがなるべくないように実験計画を立てて下さい。やむなく遅くなる場合は、指導教官 に事前に連絡すること。周りに誰もいないときにトラブルが起きると対応ができないことがあります。
・体調が優れないときは、無理せず、指導教官に連絡の上、欠席/帰宅するようにして下さい(他人への感染リスク、集 中力の低下などによる事故防止)。
●研究報告会(毎金曜日)
必ず参加すること。同じ研究室内の他のメンバーの研究内容を知ったり、質問の練習をする絶好の機会です。自分の発表スキルの上達機会でもあります。
●勉強会(論文紹介など)
必ず参加すること。参加して、世界の研究動向を知ったり、研究室の中だけでは分からない様々な知識や視点を持てるようになります。また、他の研究者の発表技術(グラフの作り方、まとめ方、論理展開など)や研究の展開ストーリーが自分の研究の参考になる場合も多くあります。当番制で基本的に研究報告会と同時に行います。
●研究経過報告会(3月、9月:半年に1回)
6ヶ月ごとに自分の実験の進捗状況についてまとめたプレゼンテーション発表を行います。
大学院生は、副指導の先生を交えたプレゼンテーション演習もあります。
●個別ミーティング
年二回4月と9月頃に行います。成績の返却や今後の研究方針、進路などについて齋藤と個別に面談します。
●レクリエーション
新人歓迎会、研究室旅行、院試・中間審査お疲れ会、スポーツ大会、忘年会(新年会)、送迎会など。積極的に参加して下さい。仲間との交流やコミュニケーションは自身の成長や様々な気づきを生み出してくれます。