まず研究,研究室とは何か?
米村研究室のポリシーを伝える前に,理科系研究室の学部の卒論研究は, 研究の入門過程ですが,研究とはどのようなものか,理解する必要があります。
第一に研究とは,これまでにわかっていないことを解明したり,これまでにない技術を開発することです。
そのために,わかっていること(これまでの文献)を調べたり,わかっていないことに進むこと, すなわち誰もよくわからないところに突き進む活動です。 このため,これまでの講義(わかっているところを知ったりすること)とは違った遥かに高度な活動になります。 そのため,教員や研究室の先輩とも話し合って(報告・連絡・相談の能力が必要),方針を考え試行錯誤を行いながら進めていきます。 なお,研究室とは研究を行う場所で,米村の認識では将来にわたって役立つことをする専門的な場所です。
このため,卒論研究は,本質的に教員・先輩がいて, 研究機材のある研究室にどれだけ来て頑張っていくかが重要なことになります。
なお,研究として進めたい方向はあっても,しっかりした研究が成立しているようだと,すでにそれは研究ではないかもしれません。 そのため,学生に対し,どこまではっきり卒論とするのかを最初から示すのは難しいことがあります。 あくまでに,見通しになります。試行錯誤を行って進めて行くのが研究ですから。

研究室で養成したい人材
大学卒および大学院卒として品格を備えている人達を養成していたいと考えています。
すなわち,専門的に社会に役立つ人材を世の中に送り出す事を大きな使命としています。 それは,どのような人材かというと,広い意味で社会に積極的に役立つ人です。 広い意味とは好きな研究に没頭して,独創性の高い新しい科学を進めることも含みます。 また,社会に役立つこととは短絡的に目の前の課題に貢献できるというより, 広い意味で科学・技術を進め,大きな意味で社会貢献できること示しています。
加えて当研究室には多くの外の人(共同研究者)と関わり合う機会があります。 その機会を通じて,自律し自分なりに価値観を作っていける人材を養成したいとも考えます。 なお,研究室(教員)の価値観に染め上げること,研究室で行われる研究の範囲で閉じ込めることは全く考えていません。
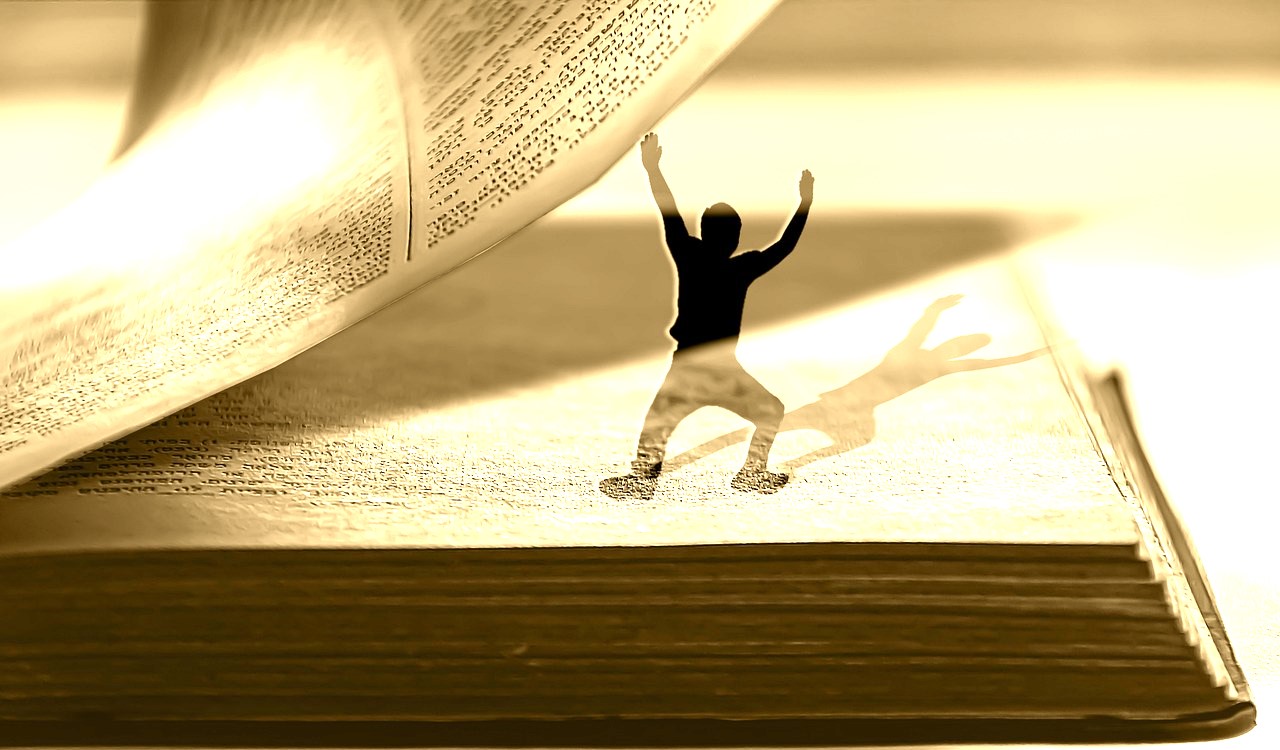
各学年の指導方針
3年生
:仕事が出来るようになること。重視するポイントは4つ。(1)研究室にしっかり来れるか:直接的な作業がない場合でも自律して研究室に来れるか。
(2)報告・連絡・相談ができるか。
(3)提出物をきちっと提出できるか。
(4)自分が出来ないことが,とても多いことを認知出来るか。

4年生
:それぞれの卒論内容を進め,学会発表レベル,さらには論文発表レベルまで進むことを目標とします。重要なのは以下の3つ。
(1)試行錯誤して進める力がついているかどうか。
(2)日々,実験か解析(モデル計算)に集中して取り組めているか。
(3)教員から示された論文を読んでいるか。
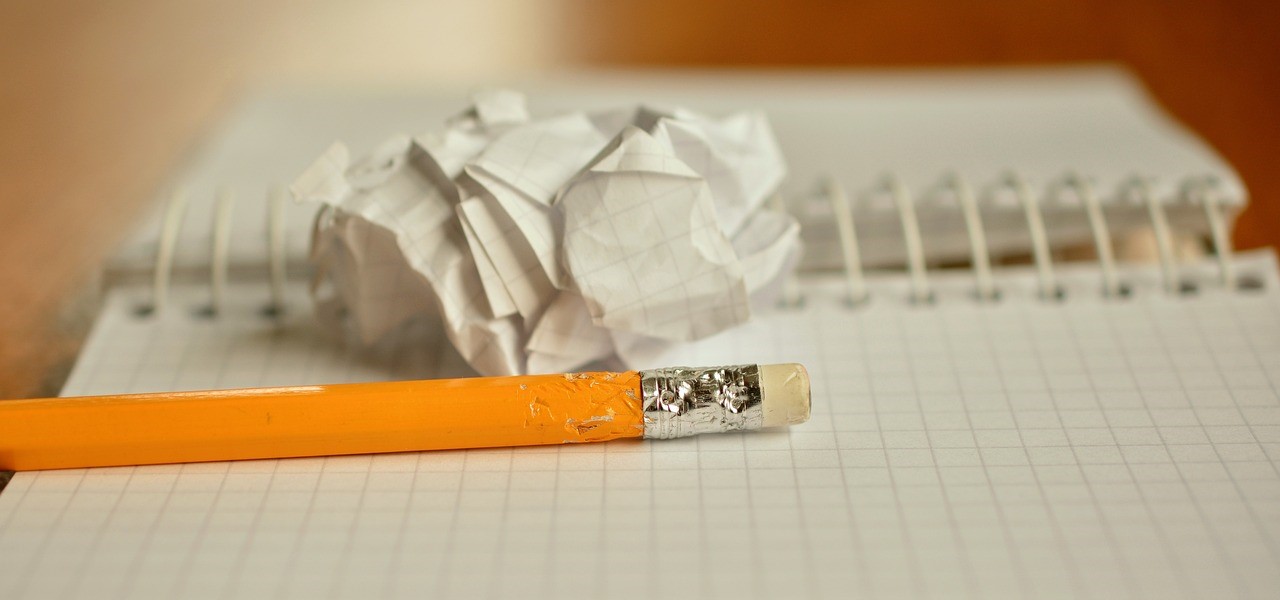
大学院生(修士)
:自身の研究を投稿論文と同等の水準に引き上げるべく,どれだけの内容を積み重ねられるかどうか?3,4年生に要求されるレベルに達しているという前提で,以下の点を重要視します。
(1)論文・文献を自発的かつ継続的に読んでいるか。その中で自らの研究の立ち位置を客観的に把握しているか。
(2)学会発表ができること。
(3)学術論文の執筆ができるか。
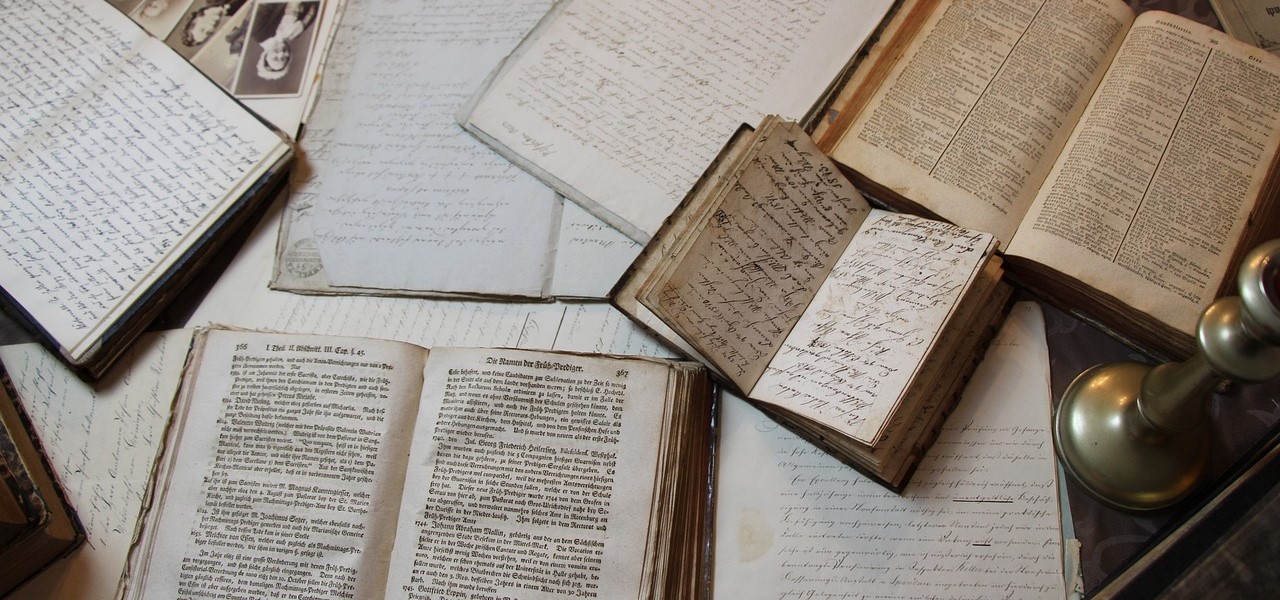 ※多くの学生にとって学術論文の執筆が,難易度は高いことは重々承知しています。
しかし,日本国外に目を向けると,修士修了の要件に学位論文と別で「学術論文の投稿」が挙げられている大学院は少なくありません。
したがって当研究室の修了生が,国内外問わず国際競争の中で「修士卒」として,十分に活躍できるよう(3)の項目を掲げています
(論文投稿が修了の必須要件ではありませんが,少なくとも執筆できる能力を得ることを目的とします)。
そのためのサポートは惜しみません。
※多くの学生にとって学術論文の執筆が,難易度は高いことは重々承知しています。
しかし,日本国外に目を向けると,修士修了の要件に学位論文と別で「学術論文の投稿」が挙げられている大学院は少なくありません。
したがって当研究室の修了生が,国内外問わず国際競争の中で「修士卒」として,十分に活躍できるよう(3)の項目を掲げています
(論文投稿が修了の必須要件ではありませんが,少なくとも執筆できる能力を得ることを目的とします)。
そのためのサポートは惜しみません。
Q&A

Q1. 先輩とのテーマの関わり合いはありますか?
A1. 研究テーマによりますが,多くの人は先輩達との関わり合いを持つことになります。
多くのテーマは先輩の研究の発展になります。
いろいろな実験・測定・分析の仕方について,先輩方から教えてもらうことになります。
Q2. どのようなことが学べますか? 「米村研究室ならでは」という視点で教えてください。
A2. 研究内容については,他のページを眺めてみて下さい。
研究室の方針としては,配属された学生を研究室の価値観で染め上げるのではなく,
共同研究・屋外調査・学会発表などの交流の中から,
幅広い視野を持っていろいろなことを吸収し,
自分自身で専門性,広い視野・価値観を身に着けてもらうことを目標にしています。
これは,研究室が大気というものを大きな要素として考えていますが,
大気はいろいろなものと関係してくるというところから来ているとも言えます。
・留学生がいる研究室です。是非,英語で沢山話してほしいです。
・大学院生は,海外での調査・学会発表に参加しています。
・学際性がとても強い研究室です。研究室の研究内容は様々な方向に延びています。
Q3. 成績(GPA)は定員オーバー時の選考に影響しますか?
A3. 影響します。これについては,他の研究室でも同様だと思います。
GPAが一定値より低い場合には,面接をする予定です。
Q4. コアタイムはありますか?
A4. 本来の研究活動は,研究のスケジュールに合わせて時間管理していくものです。
そのため,自らスケジューリングする能力を身に着けてほしいです。
すなわち,自らコアタイムを設定していく感じかと思います。質問する人にはコアタイムを設定したいと思います。
なお,研究が進むかどうかは,これまで学生を見てきて,研究室にどれだけいるかで決まっています。
Q5. 就職活動で研究が止まった期間があっても,卒業できるでしょうか?
A5. 出来ますが,程度によります。
Q6. 研究室内の提出物・発表などの頻度を教えて下さい。
A6. 毎週,研究室集会で,報告をおこなってもらいます。
また,3か月に1度程度10ページのレポート(大進捗報告といっています)を提出してもらいます。
なお,研究をおこなったことをしっかり科学的に記録していくことは,研究する上での基本姿勢です。