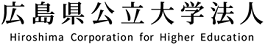本文
住居 広士(すみい ひろし)
研究者紹介

所属: 県立広島大学大学院保健福祉学専攻 職位:特任教授 学位:医学博士
研究室:三原キャンパス 2505
E-mail: sumii*pu-hiroshima.ac.jp *を@に変えてください。
研究内容:https://researchmap.jp/read0047607
研究室Web: https://jp.carework.org/
研究に関する自己PR
広島県は,政令指定都市から中核都市ならびに沿岸諸島部から中山間地域の市町村に至る全国にわたる地域の多様性と個別性の縮図から構成されている。近年の加速する少子高齢化に対応が困難となる地域も多く,まさに日本の近未来の長寿社会を象徴する地域になっている。特に生活課題を抱える高齢者等は社会的弱者となり,家族や地域社会との交流が乏しくなり,自立した尊厳のある生活を失いつつある。高齢者等も多世代共生により,共に多様で個別な社会活動に常時参加できるコミュニティである長寿活力社会が求められている。
広島県内には保健福祉活動による地域協働型を基盤とした多世代共生コミュニティの構築や維持による長寿活力社会の創出に成功しつつある事例がある。成功事例から,多世代共生コミュニティを構築して地域活性化につなげ得るのか,高齢者保健福祉的視点から解析して具体策を創出することは必要性が強く価値が高い。そのような成功事例を強化するための介入因子を通じて地域の特殊性を超えた一般性を備えた長寿活力社会を地域包括支援する必要がある。その問題の本質的な解決に繋がる自立した尊厳ある生活の基盤となる多世代共生の社会,生きがいを実感できるコミュニティの構築とその実践,地域社会の健康と活力を取り戻す長寿活力社会の確立に貢献する高齢者保健福祉活動の地域包括的実践が待ち望まれている。地域の特殊性と共通性に応じた多世代共生のコミュニティの構築と維持とそれらによる地域住民の健康の保持と長寿活力社会デザインを提唱する。
研究テーマ
1. 地域協働型の多世代共生によるコミュニティで支える持続可能な長寿活力社会
2. 介護モデル構築に関する理論と実践―介護保険総合研究に向けて―
3. 介護保険における介護サービスの標準化と専門性
4. 介護福祉学の教育・研究から学術の役割と発揮
5. 保健福祉から医療介護による地域包括ケアの長寿活力社会デザイン
研究の特徴・内容
人口が多くピラミッド型をしていた時代に創られた現行の社会デザインを,人口の少子高齢社会から人口減少社会を迎える日本では,地域協働型の多世代共生による長寿活力社会のデザインに創り直すという社会的課題を解決していく必要がある。人口の少子高齢化や減少化に対して,従来の国益のために分業化された学術分野における個別的な科学的成果を集積するだけでは,実践的な包括的な成果として有効に貢献をすることが困難である。人口の急速な少子高齢化と減少化を迎える日本では,持続可能な社会に向けた問題解決を図っていくが重要な課題である。社会が望む少子高齢から人口減少社会のあり方を,地域協働型の多世代共生による長寿活力社会のデザインの創設を提唱する必要がある。その社会デザインの仕組みと機能が,今後の少子高齢社会から人口減少社会の課題解決に不可欠である。地域社会の視点では,地域住民が安心して豊かに暮らし続ける地域社会を活性化することには多世代共生のネットワークの構築が必要であり,地域協働型の多世代共生で支える長寿活力社会の実現が,コミュニティで創る少子高齢社会から人口減少社会のデザインとなる。
論文リスト
著書
知財リスト
著作権: 論文・著書・報告書他多数
専門資格
医師・社会福祉士・介護福祉士等
キーワード
介護福祉、保健福祉、医療介護、医療福祉、老年学等
関連するSDGs項目

関連情報
高齢者の健康分科会委員長,日本学術会議連携会員・日本介護福祉学会・理事, 日本保健福祉学会・理事等
〇介護の理論と実践により福祉を実現する介護福祉学の研究他多数
わが国の人口の少子高齢化は、いまだかつてないスピードで進展している。加齢に伴い障害は、複合障害を有し、包括的管理が必要とされ、保健福祉関係者が果たす役割が重要となる。この少子高齢化に、多方面から対策や研究が期待されている。この長寿科学に対して、職種ごとに課題を設定し、今後の長寿社会に向けた対策や研究についてまとめ、さらに少子高齢化をとりまく、各職種間での連携と総合化の必要性について研究する。
介護福祉学に関する研究
(1)介護福祉学を中心に,高齢者や障害者等を取り巻く課題に対して,介護福祉学に基づく介護モデルについて研究を行う。介護福祉学の探求を図るために,介護福祉学に関する理論的学問ならびに実践的専門性を包括しながら,その課題の発見・認識・解決・評価へ,教育と調査研究の過程を専門的に展開し,介護の実践により福祉を実現する介護福祉学体系を研究する。
(2)介護福祉学の研究課題を構築するために必要な保健・医療・福祉的専門知識,ならびに介護保険制度等をめぐる理論的と実践的研究を行う。介護福祉学に関連する実践現場に関与し,理論的かつ実践的知識と技術の探求を図る専門的研究を行う。介護福祉学の研究計画・展開過程・研究評価を研究しながら,保健・医療・福祉等の諸科学を展開する専門教育と介護過程を研究する。
(3)現在の介護福祉学の研究の課題点について,介護福祉学を探求する評価法と分析法を研究する。介護福祉学に基づく調査研究ならびに研究教育を実践できるように研究する。少子高齢社会において尊厳のある生活のための介護モデルに基づく介護福祉学について考察を深めて,研究論文等と著書の作成を目指す。その研究課題ならびに論文を提示しながら,調査研究を展開しながら,介護福祉学の理論と実践の探求過程から学術的水準を上げるように研究する。
 大学概要
大学概要
 学部・大学院・専攻科
学部・大学院・専攻科
 学生生活・就職支援
学生生活・就職支援
 研究・地域連携・国際交流
研究・地域連携・国際交流
 入試情報
入試情報