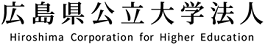本文
【環境科学コース】 コラム:環境と微生物
コラム:環境と微生物
今回の記事では、環境科学コースに所属する教員(有馬 寿英)の研究に関わるコラムを紹介します。
「環境と微生物」というと、皆さんは何を思い浮かべますか?“地球環境と微生物”あるいは“環境問題と微生物”、というのがまずはありますかね。何れにしても、微生物は何らかの形で係わっていると思われます。本学科及びコースでの講義内容などからは、少し細かくなりますが、“水環境と微生物”や“土壌環境と微生物”というのがあります。皆さんは気づいていないかもしれませんが、どちらも我々が日常生活を送る上ではホントに大切です。そのため、ここでは複数の視点からの「環境と微生物」について、取り上げてみようと思います。
近年お熱を出している地球さん、その地球さんでの微生物の主なお仕事は「分解者」、すなわちお掃除屋さんです。我々ヒトを含む動物などが出すゴミを、毎日せっせと人知れず掃除してくれており、地球が生きていくための仕組みでの重要なメンバーです。もしお掃除屋さんである微生物がいなくなると、地球さんはゴミだらけになってしまうかもしれません…、困りましたね。地球さんの環境を守るためにお仕事をしている微生物で、皆さんが知っているであろうものの一つが“キノコ”です。キノコは倒れた木などを分解するために大切な役割があるのですが、その一方では、木が持っていた二酸化炭素を開放することにも係わっています。一長一短…、でも地球さんにとってはどちらが良いのかは、チョットばかり皆さん考えてみてください。
蛇口をひねれば飲めるお水が簡単に手に入り、そして汚れた水をきれいにする施設がたくさんある日本、このような国はそう多くはありません。皆さん、日々の暮らしでの水道水や下水処理の有り難味を実感していますか?多分、ほとんどの方が何のことやら…、だと思われます。それ程ありふれた日常であり、かつ当然のこととして過ごせるのは素晴らしいことですよ、きっとね。特に下水の処理では、地球さんでの主なお仕事と同様、微生物は「分解者」として活躍しています。ヒトが出す排泄物や排水などを、下水を処理する施設にある大きな水槽のようなものの中でチョットずつ、そしてコツコツと微生物が分解しています。これを少しばかり難しい言葉にすると“活性汚泥処理”というのですが、分かり易くすると、砂粒のデコボコをお家にしている微生物が排水などに含まれている物質をご飯にし、窒素やリンなどの濃度を下げている、ということです。かなり大雑把ではありますがね…。
「あなたの体は9割が細菌」と言われて、皆さんは信じることができるでしょうか?でも、このタイトルの文庫本が河出書房新社より刊行されています。皆さんピンとこないかもしれませんが、我々ヒトは微生物に住み家という環境を提供している大家さんなのです。その一つが、近年注目が高まっている“腸内細菌(あるいは腸内フローラ)”という言葉です。腸内細菌はたくさんの微生物の集まりであり、日々の体調、そして少し大げさかもしれませんが脳までもコントロールしていると考えられています。出産の方式によりますが、腸内細菌はお母さんから生まれてくる子供への最初の贈り物、とも言われています。贈り物である腸内細菌をうまく受け取れないと、将来、その子供は現代病と言われているアレルギーや肥満などの疾患に苦しむことになるかもしれません。人生100年時代に向かう子供には、ホントに大変なことなのです。
微生物は植物や動物よりもはるかに小さい存在ですが、お外からの刺激に単純に反応する機械のようなものではありません。それぞれのやり方でお散歩やおしゃべり、食事などを日々きっと楽しんでいることでしょう。見えていないだけで、微生物はそこら中にいます。雑木林やみかん畑、食べ物や薬の中にも、さらには私たちのお家や体にまで。たまに脅かすことがありますが、微生物がいかに私たちの暮らしを豊かにしていることか…。微生物の世界に足を踏み入れるには、「そこにいる」と知ることが大切なのでしょう。
=========================
さらに詳しく知りたい方はこちら!
・環境科学コースウェブサイト …環境科学コースについて紹介しているサイトです。
・環境科学コースに関するブログ …環境科学コースに関する記事をご覧いただけます。
・有馬助教 …有馬助教の紹介をしています。
 大学概要
大学概要
 学部・大学院・専攻科
学部・大学院・専攻科
 学生生活・就職支援
学生生活・就職支援
 研究・地域連携・国際交流
研究・地域連携・国際交流
 入試情報
入試情報